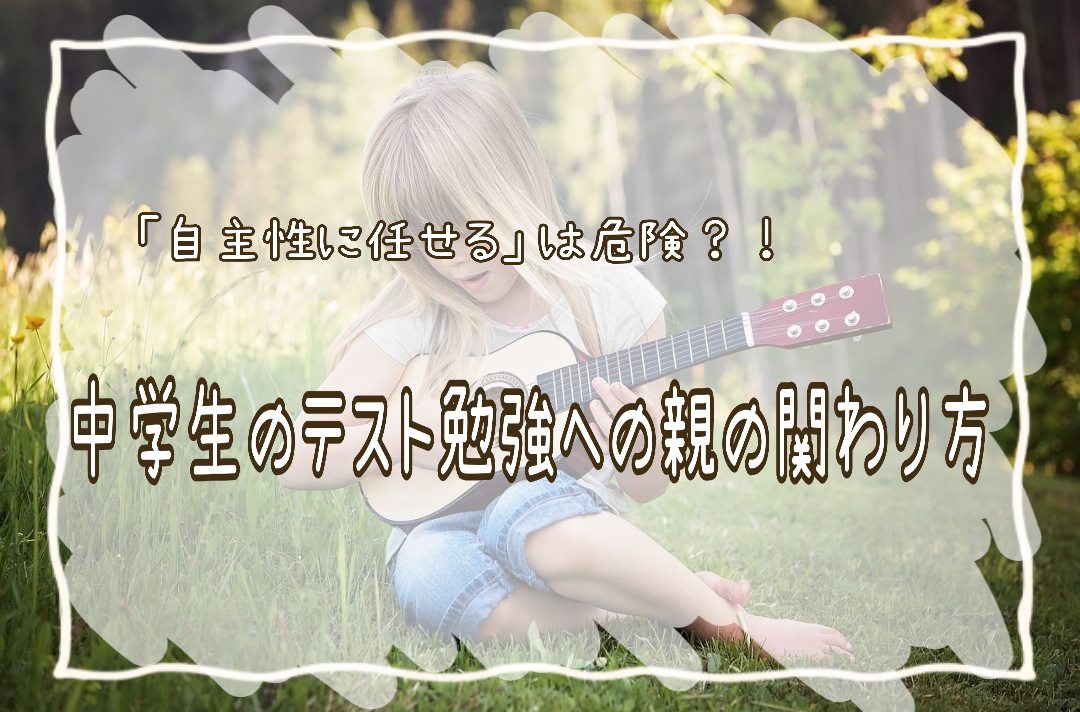塾やネットの情報などで
「子供の自主性を尊重して親は口出ししないで見守りましょう」
「子供に任せた方が自立心が育ちます」
と言われ、中学生のお子さんのテスト勉強に何も関わらなかったら、
「全然成績が上がらない」「勉強しないけどこのままでいいの?」とお悩みの方も多いでしょう。
本当に中学生の勉強に親はノータッチであるべきなのか、
そんなお悩みをお持ちの方に、中学生のテスト勉強への親の関わり方についてお伝えします。
目次
親は中学生の定期テスト勉強に関わるべき?
小学校から中学校に上がると、クラスの雰囲気や授業の雰囲気もガラッと変わります。
小学校では時々行っていたペーパーテストが、
中学校では2週間ほど前に定期テストの範囲が発表され、テストに向けて勉強をして、
結果や順位が発表され成績に反映し、高校受験にも関係してくるのです。
「テスト勉強に親が口出しをすると自主性が育たない」などと良く言われますが、
結論から言うと、勉強しない子どもを放置するのはNG。
「本人の自主性に任せる」と「放任」は同じように見えて別物。
親がサポートしない状態で子どもが自主的に勉強するようになるわけではありません。
成績が上がらない生徒や成績が悪いお子さんは、友人関係やスマホなど目先の楽しいことに時間を取ってしまい、
放っておいたら勉強をしないままというケースが大半です。
また、小学校からの学習内容をきちんと理解できていないなど基礎学力がないお子さんは、
中学校の内容を理解することが難しく、授業についていけない可能性があります。
それなのに、「自主性に任せる」「自分のことは自分で」という理由で
親御さんがお子さんの勉強に無関心でいると、勉強がわからない→楽しくない→勉強しない
という悪循環に陥ってしまいます。
中学の三年間はあっという間で、日々の学習内容が積み重ねとなってきますので、
基礎学力が身につかないまま受験を迎えることになってしまいます。
学習習慣が身についていないお子さんは、勉強のやり方を親が伝え、サポートが必要です。
しかしながら、過度な干渉は子どもの自主性を損ない、勉強へのモチベーションを下げてしまうおそれがあります。
大切なのは、親が適切なタイミングで関わることです。
それでは、どのように関わっていけばいいのかいいのでしょうか?
具体的に見ていきましょう。
勉強ができない理由に子供が自分で気づくのは難しい
自主性に任せるために勉強しない子を放置するのは危険です。
何度、注意しても勉強しないお子さんに「じゃあもう自分でやりなさい!」と、
放っておきたくなることもありますが、これは良く言えば「子どもの意思を尊重する」ですが、
この対応は果たして正しいのでしょうか?
・勉強できない理由に気づくサポート
・勉強に集中できる環境づくり
・子どもの相談に乗る
・勉強のサポート
勉強ができない理由に気づくサポート
勉強ができない主な理由には、「学習しているレベルが学力に合っていない」ケースと、
「勉強のやり方がわからない」というケースがあります。
子供の勉強を放置すべきでない理由には、
そもそもこの二つの理由にお子さんが自分で気づくのが難しいということにあります。
わからない→難しい→解けない→勉強はつまらないというループに入ってしまいます。
親のサポートのもとで勉強ができない、成績が上がらない原因を発見し、
レベルに合った教材を見つけたり、レベルに合わせて少し戻ってみたり、
勉強のやり方を親や塾などのプロに教わるなどの対処をすることで
自分で問題を解く、勉強がわかるということに繋がります。
勉強のやり方がわからないために、やる気が出ないというケースもあります。
わからない部分の調べ方や考え方、効率の良い暗記の方法、
わからない箇所を自分で解決する力を身につけることで、
自分で答えにたどり着く方法が身に付き、勉強がわかることで次の問題を解く力になっていきます。
・テキストが学力に合っているか?
・勉強の「やり方」を教える
勉強に集中できる環境づくりのサポート
お子さんの勉強している環境に目を向けてみましょう。
リビングで学習をしているお子さんや、自分の部屋で学習をしているお子さんなど様々でしょう。
勉強に集中できる環境は整っていますか?
机の上が勉強で関係のないもので散らかっていたり、
すぐに手に届くところにゲームやスマホ、マンガなどがあったりすると集中できません。
また、早寝早起きや食事はきちんと食べるなど、生活習慣を見直したりすることも親のやるべき関わり方です。
また子どもが勉強しているときは、邪魔しないようにテレビを消したり、
近くでスマホを操作したり気が散らない気遣いも重要です。
集中できる環境作りや体調に気を遣うのも大切なサポートです。
子供の相談に乗る
子どもが勉強や学校のことで相談してきたら、悩みごとや不安を親身に聞いてあげることが大切です。
勉強に関することだけでなく、「友達のことで悩んでる」など、
身近な悩みや不安を気軽に相談に乗れる存在は子供にとって心強いものです。
中学生になると思春期に入るため、悩みごとを抱えやすくなります。
悩んでいると勉強に集中できないため、子どもの様子に変化があったら、声をかけてあげましょう。
困ったら話を聞いてくれるということが、お子さんの気持ちの安定にも繋がります。
そのためには普段からコミュニケーションを心がけましょう。
中学生になるとなかなか話をしてくれなくなるお子さんも多いでしょう。
お子さんの話に耳を傾け、真剣に聞いているという姿勢が大切です。
過去の記事はこちら→子どもの話を聴くときにやってはいけない親のNG行動と聞き上手になるポイント!
中学生の定期テスト勉強のサポートは具体的にどんなこと?
勉強のサポートといっても、親が勉強をするわけではないので、どのように関わればよいでしょうか。
基本的には自分で学習を進め、過度に関わりすぎず子どもが必要とした時に適度に関わることが大切です。
・一緒にスケジュールを考える
・添削をする
・問題を出し合う
一緒にスケジュールを考える
定期テストの際には約2週間ほど前に範囲が発表になり、
部活や学校生活を送りながら効率よくテスト勉強を進めていくスケジュールを考えるのは、
最初は難しいため、最初のうちは一緒に計画を立ててあげましょう。
特に勉強の習慣がない子の場合、勉強の計画を立てることに慣れていないため、サポートすることが大切です。
2週間の間にある予定や、勉強にどのくらいの時間を使うことができるのか、
どの教科にどのくらい時間がかかりそうかを一緒に話し合いながら、無理のないスケジュールを立てましょう。
ここで大切なことは、「子どもの意見を聞き、決定権は子どもにある」ということ。
一見、親子で話し合いながら決めたように見えても、
「これをやったほうが良いよ」「このほうが良いよ」と口を出しすぎると、
子どもが「親に決められた」と感じ、勉強をやらされているという気持ちになってやる気も上がりません。
予定や勉強量などを話し合いながら、「この日は数学のドリルをこれくらい進める」など
具体的な決定は子どもに委ねましょう。
勉強は小さな達成感を積み重ねていくことが重要です。
「〇点以上取る!」という目標は結果であって、結果が全てになってしまいます。
小さな達成感は「毎日10分ドリルを解く」など行動目標を達成することで味わうことができ、
小さなハードルを「乗り越えた!」という気持ちを積み重ねていくことで力になっていきます。
そして、小さな目標を達成できたら褒めてあげましょう。
厳しすぎるスケジュールを立てて、スケジュール通りに行かないとやる気も落ちてしまいます。
無理のない量とスケジュールで、毎日「達成できた!」という気持ちを味わえるようにサポートしましょう。
添削をする
子どもが解いた問題の丸つけや添削をしてあげることも、親が子どもと一緒に勉強する適切な方法の1つです。
問題を解いた後にわからなかった問題を把握することは、成績を上げるには大切なことです。
学習に慣れていないお子さんは、適当に丸を付けてしまったり、
丸付けをしながら正解を書き込んで、再度解き直しをしないなどのケースがあります。
また、自己採点が甘く自分では〇をつけていたのに、
実際のテストの際にはその答え方では×になってしまうという場合もあります。
全て問題を解き終わった後に自分で丸付けをすると、
もう勉強が終わった気分になって、その後の解き直しに力が入らないお子さんも多くいます。
継続して丸つけや添削をしていくと、わからないところを減らすことができるので、
苦手に気づき、テストの点数アップが期待できます。
問題を出し合う
暗記などは自分一人で教科書を読んだり書いたりするよりも、
親子で重要なポイントをクイズ形式で出し合うことで、
効率的に暗記・理解できるというメリットがあります。
クイズを出し合うことで、子どもが理解できていない部分を把握でき、
話しながら問題を出し合うことで、暗記する語句も印象が残り易くなります。
さらに、子どもが出題者としての視点に立つと、
出題の意図がわかりその問題の理解が深まるため効果がアップしますよ。
中学生の定期テストの結果についての親のNG対応
それでは、実際にテストが終わって点数が思っていたより悪かった場合、
親はどのように対応すればよいでしょうか?
親のテスト結果へのNG対応は次の通りです。
・点数を見てただ叱る
・子どもを否定する
・人と比べる
・罰を与える
点数を見てただ叱る
点数を見て、その点数が思っていたよりも悪いことを衝動的に叱るのはやめましょう。
本人は点数に関して、落ち込んでいたり気にしているかもしれません。
また、その時は難しいテストで平均点が全体的に低い場合もあります。
そのため、前回80点だったのが今回60点に落ちたからと言って
必ずしも「できなかった」とは限らないのです。
「だから勉強しなさいって言ったじゃない!」
など頭ごなしに叱るのは、逆効果になります。
点数を叱ることで、それ以降、都合の悪いものを隠すようになってしまう子もいます。
次の反省点を見つけて活かしていくためにも、点数を見てただ叱るのはやめましょう。
子供を否定する
「頭が悪い」「あなたはダメね」など子供の人格を否定するような発言は絶対にやめましょう。
子供の自信を奪い、今後のやる気やモチベーションを下げる結果になります。
勉強嫌いになるだけでなく、自己肯定感も下がり、親に対する不信感にも繋がります。
人と比べる
「お兄ちゃんは〇点だった」など他の人と比べられるとやる気も下がってしまいます。
人と比べるのではなく、本人の今までの勉強してきた努力や過程を見て声をかけてあげることが大切です。
罰を与える
テストの結果の罰として、スマホを没収したりゲームを没収したりすることはやめましょう。
遊ぶ時間が息抜きになっている場合、その時間を奪うことでやる気がますます落ちてしまいます。
テストの結果を見て、「ゲームの時間を取りすぎた」「スマホを見ていて気が散ってしまった」
など子供が自分自身で点数が伸びなかった原因として感じている場合は、
親子で話し合ってゲームやスマホなどのルールを決めましょう。
一方的に罰として取り上げることは、親への反発に繋がります。
中学生の定期テストの結果に対する親が取るべき対応
テストの結果についての親のNG対応を見ていきましたが、
それでは、親はどのように対応するべきでしょうか?
・次に向けて反省点を話し合う
・子どもが結果についてどう感じているか聞く
・努力の過程を認め、成長した点や良い所を褒める
次に向けて反省点を話し合う
テストの結果はもう終わってしまったことなので、それについて叱るよりも
今回の反省を活かして次にどうすればいいかを話し合いましょう。
その際は点数について責めるのではなく冷静に、
「今回は漢字が点数とれてなかったから次はどんな風に勉強しようか?」
「時事問題を落としてしまったから、次はどうすればいいと思う?」
など具体的に解決策を話し合いましょう。
その際に、「~しなさい」という強制ではなく、
「どうしたらいいと思う?」「~するのはどう?」など自分で考えさせたり提案をしましょう。
点数よりも間違えてしまった内容を確認し、何をどのように間違えてしまったのかに気づくことが大切です。
きちんとテスト後に見直しをして、対策を取ることで同じ間違いをしないようにしましょう。
子供が定期テストの結果についてどう感じているか聞く
テストの結果は親以上に子供が気にしている場合があります。
親がどう思ったかを伝える(叱る)よりも、先に本人が結果についてどう感じているかを聞きましょう。
ショックに感じている場合は、共感してあげることで子どもは親を信頼します。
テスト結果を冷静に振り返るためにも、まずは子供の気持ちに寄り添うことが大切です。
努力の過程を認め、成長した点や良い所を褒める
点数を見て頭ごなしに叱るのではなく、テストについて良い点を褒めてあげましょう。
「丁寧に書けてるね」
「前に間違えた問題が正解してるね!」
など、成長がみられる部分を褒めてあげることが大切です。
テストの点数が思い通りでなくても、テスト勉強やテストを頑張ったことをまずは褒めましょう。
中学生は悩みもいっぱい 放置しないで寄り添う
中学生は環境や友人、勉強、部活など様々なことに不安や悩みを抱える年頃です。
その中で親への反抗的な態度や勉強しないなどについイライラしてしまうこともあるでしょう。
そこで「もう勝手にしなさい!」などと放置してしまうと、
勉強がわからないまま進んでしまう、成績が下がってくるなどの悪循環になることもあります。
放置しないで、過剰に関わりすぎない適度な距離感で、
子供を信頼しながらもサポートをしてあげることが大切です。
テストの結果だけを見て判断するのではなく、そこに至る過程や内容など
様々な視点で冷静な対応をすることが重要です。
中学生の定期テスト勉強の「やり方」がわかるおすすめ本

中学生の勉強法ver.2.0
昔から変わらない中学生の勉強にとって大切なことに加え、最新の課題に対応するべく、バージョンアップした勉強のやり方がわかる本。子どもに話しかけるような優しい文脈で読みやすく心に響く一冊です。

中学生からの勉強のやり方(新学習指導要領対応・改訂版)
「勉強のやり方」が身につけば、 すべてがうまく回りだす!「勉強のやり方」がわかれば、勉強がどんどんわかるようになります。わかるようになれば成績が上がる。「できる」「解ける」喜びも味わうことができる。そうすると、さらに学びたくなる。いい循環を生み出すメソッドで勉強ができるようになるサポートをしてくれます。

塾へ行かなくても成績が超アップ! 自宅学習の強化書
学校以外に、お金を払って塾へ行ったり、通信教育を受けることだけが、成績を上げる方法ではありません。2020年3月、新型コロナウイルスの影響でまさかの全国一斉休校、そこから急にスポットライトを浴び始めた自宅学習もまた、それらに勝るとも劣らない次のような強みを秘めています。自宅学習の進め方をわかりやすく解説してあります。

勉強大全 ひとりひとりにフィットする1からの勉強法
東大生クイズ王・伊沢拓司が、自身の「勉強法」を一から解き明かします。高校時代、クイズ界で「知識のモンスター」として名を成すも学業がおろそかになり、成績は学年で下から数えるほどに。そこから東大受験突破にいたるまでに伊沢氏が分析し、実践した「勉強法」を伝授します。
まとめ
子供のテストの点数が悪いからと言って感情的に叱るのではなく、
次に向けてどんなことをすべきか、親として何ができるかを冷静に判断しましょう。
相談に乗ったりサポートしたりできることはしっかりと関わり、
自分で考えるべきことは任せるなどのバランスが大切です。
成長や頑張りは積極的に褒めて、やる気を引き出しましょう!