テスト結果を見て「うちの子読解力大丈夫?」と心配になる親御さんも多いのではないでしょうか?

子どもの読解力を上げるにはどうしたらいいの?
実は国語だけでなく、全ての教科で読解力は非常に重要です。そこで、今回は読解力を上げるための家庭でできるトレーニング方法をご紹介します。
【関連記事はコチラ】
作文の書き方のポイントは?4つのステップでサラサラ書ける作文のコツを解説!
【おすすめ本】学習まんが「世界の歴史」をまとめて買って一気読み!わかりやすさが魅力の角川まんが学習シリーズ!
中学生が読むべきおすすめ本15選!ジャンル別に紹介・本を選ぶポイントもチェック!
小学生がスケジュール管理を自分でできるようになるには?役立つメリットがいっぱい!

目次
- 【読解力トレーニング】そもそも読解力とは?
- 【読解力トレーニング】日本の子どもたちは読解力が低下している?
- 【読解力トレーニング】なぜ読解力が低下しているのか?
- 【読解力トレーニング】なぜ今読解力が必要なのか?
- 家庭でできる子どもの読解力を高めるトレーニング
- 読解力アップにおすすめの本
- 読解力トレーニング まとめ
【読解力トレーニング】そもそも読解力とは?
そもそも読解力とは何でしょうか?
読解力とは、「文章を読んで意味を正しく把握し理解する力」です。文章に含まれる情報を正しく理解し、意味を把握する能力のこと。基礎的な読解力は文章の中から意図や内容を理解する力が必要ですが、そこから発展して主旨を把握して的確に答え、自分の考えをまとめる力も必要です。
また、学年や年齢が上がるとともに、論理的な読解力などさらに高度な力が必要になります。まず思い浮かぶのは国語のテストなどで文章を読んで答える問題かと思いますが、読解力は国語だけでなく、社会や理科、算数など様々な教科で必要になります。
算数ではいくら計算が得意でも、文章題を読んで意味をしっかりと理解できないと解けませんし、社会や理科でも文章の中から出題者の意図をしっかりと把握しないと答えにたどり着けません。文章を読み解く力が足りないと、様々な教科で点数が伸び悩むことになります。
読解力は次の4つの要素で成り立っています。
| 語彙力 | 言葉の意味を正確に読み取る力 言葉の意味を知らないと正確に文章を読み取れないため、言葉の意味を正確に把握し理解できる力。 |
| 解釈力 | 文章の構成を理解する力 文章のパターンに気づき構成を意識しながら読むことで論点を素早く正確に理解する力 |
| 要約力 | 文章の内容を自分なりにまとめる力 文章を自分の言葉で発信できるように内容をまとめることのできる力 |
| 速読力 | 時間内に読み終える力 語彙力や解釈力を鍛え、基礎的な能力を上げることで自然と早く読む力が身につく |
これらをトレーニングしていくことで、読むスピードと正確さを上げていけます。
【読解力トレーニング】日本の子どもたちは読解力が低下している?
日本の子どもの読解力は近年はどのようになっているのでしょうか?
3年に一度、15歳を対象に国際学力テストを実施している文部科学省の国際学力調査(PISA)の調査によると、2018年では日本の子どもの読解力は前回の8位から15位と大きく順位を下げていることがわかります。
数学や科学分野では高い水準である一方で読解力は学力が低下しているのです。
【読解力トレーニング】なぜ読解力が低下しているのか?
読解力の低下にはいくつか理由があります。
SNSが主流になり短い文章でのやり取りが増えた
SNSを使用したコミュニケーションでは、短い文章でスピーディーなやり取りが増えました。
そのため、長文を読んだり書いたりすることが減り、長文の中にある意図や気持ちを読み解く機会が減ったことが原因の一つです。
お子さんがお友達とメールのやり取りをしている画面を見たことがあるでしょうか?最近の子どもたちのメールの特徴として「文章が非常に短い」という点が挙げられます。
「明日ヒマ?見たい映画あるんだけど行かない?」といった短い文章であっても、
「明日ヒマ?」
「映画見たい」
「行かない?」
という風に短く分けで都度送信しているお子さんが多く、一つひとつの文章が非常に短く接続詞や長い文章を打つ機会が少ない点が特徴的です。
短い文章を読むことに慣れると、長文を読むのが面倒になったり、長い文章を作成する頻度が減ったりして、そもそも長文に触れる機会が減ってしまうのです。絵文字で気持ちを伝えるなど、言葉にする機会が少ない環境も影響しています。

確かに短い文章でポンポンやり取りしているかも
略語やスラングによって正しい日本語を使う機会が減った
スラングは特定のグループ間で使われる言葉で、若者を中心に、略語や造語を遣う機会が増え、正しい日本語を使う機会が減少しています。これによって語彙力の低下という現象が起きています。
例えば「ヤバい」という言葉は「とてもすごい」「おいしい」「かわいい」「非常に悪い」など様々な意味を持っています。様々な場面で「ヤバイ」の一言で済ませてしまうことが、語彙力の低下へと繋がっていきます。
このように様々な場面で使える便利な言葉が増えることで、情景を正しく言葉で伝えたり、読み取ったりすることが難しくなります。

子供たち「ヤバい」ってよく使うわ…
活字に触れる機会が減った
動画配信やゲームなどのコンテンツが増え、本などの文章を読む機会が減っています。動画では視覚だけでなく聴覚から入ってくる情報も併せて理解するため、文章を読んで想像する必要が無くなってしまいます。
動画やゲームなど簡単に情報を得られるコンテンツになれることで、本を読むことが面倒になってしまい読む機会が減っていってしまいます。
一方的な情報発信・部分的な切り取りで判断することが増えた
SNSや動画配信などにより、自分の考え方を発信することが増えています。それ自体はとても良いことだと思いますが、「自分の言いたいことだけを一方的に言う人」が増えてきていることが気になる点です。また、他者が発信している内容についても、相手の言い分や文脈を無視して、一部分だけを切り取り自分が反応したいように反応している人も多く見受けられます。
全体を見ずに一部分だけを読むことで読み間違いや誤解が生まれます。これはまさに文章読解の苦手な人がテストでやってしまう失敗と重なるのです。

【読解力トレーニング】なぜ今読解力が必要なのか?
それではなぜ読解力が必要なのでしょうか?どのような場面で必要なのでしょうか?

読解力は全教科に関係してくる
読解力は国語の文章題だけに必要な力ではなく、全ての教科に必要な力です。関係がなさそうな算数でも、文章題など文章を理解した上で回答する問題はたくさんあります。的確に問題を把握しないと答えにたどり着けない問題はどの教科にもあります。また、読み解くスピードが遅いと、全体の問題を時間内に解けないという事態にもなります。スピーディに正しく読む技術は読解力を鍛えることで身につきます。
問題の最後に「記号で答えなさい」と書いてあるのに言葉で答えてしまった、「間違っているものを選びなさい」と書いてあるのに正しいものを選んでしまったといったケアレスミスも、細かな部分までしっかりと読めていないことが原因で起きています。
近年入試は長文問題・情報処理能力が求められる
中学受験や高校受験、大学受験などは近年、どの教科も問題の文章が長文になり、資料やグラフなどを駆使して情報処理能力や思考力が求められるようになってきました。公立高校の入試問題でも問題の文章だけでも長文になっていて、素早く正しく読み取る力を求められます。問題を見ただけで諦めたくなるような長文も多く、文章を読むことに慣れ、読解力を鍛える必要があります。
社会に出た時にも必要な力
仕事をする上でも読解力は非常に重要です。資料などの文章を読み解き、相手の意図を汲み取って商談を行うなど、スピーディーに的確な判断を行うために読解力が重要になってきます。
大切な部分の意図が読み取れていないと仕事にも支障をきたしてしまいます。
読解力があると資料や報告書の要点を素早く判断し、相手の伝えたいことを的確に判断できます。また、どのように伝えれば相手が理解しやすいのかもわかるので説得力が増すのです。
人付き合いにも関係する
読解力は、気持ちや相手の考えていることを汲み取る力が身に付きます。そのため、読解力が高い人はコミュニケーション能力にも秀でている場合が多く、相手がどう考えているか、この後どのように立ち回ればいいかの判断が上手い人が多いのです。
話し合いなどの場でも、読解力は大いに役立つため、今後の学校生活や社会生活でも役に立ちます。
家庭でできる子どもの読解力を高めるトレーニング
子どもの今後に大きく役立つことが分かった読解力ですが、具体的にはどのようにすれば読解力を高められるのでしょうか?
お子さんの読解力を高めるために家庭でできるトレーニングをご紹介します。

まずは4つの要素を意識する
先ほど挙げた4つの要素を意識してトレーニングをしていきましょう。
| 語彙力 | 言葉の意味を正確に読み取る力 言葉の意味を知らないと正確に文章を読み取れないため、言葉の意味を正確に把握し理解できる力。 |
| 解釈力 | 文章の構成を理解する力 文章のパターンに気づき構成を意識しながら読むことで論点を素早く正確に理解する力 |
| 要約力 | 文章の内容を自分なりにまとめる力 文章を自分の言葉で発信できるように内容をまとめることのできる力 |
| 速読力 | 時間内に読み終える力 語彙力や解釈力を鍛え、基礎的な能力を上げることで自然と早く読む力が身につく |
4つの要素をバランスよくトレーニングしていく方法を次に解説していきます。
速読力:本を読み活字への抵抗感を減らす
「読解力にはやっぱり読書か…」と思った親御さんも多いでしょう。まずは、読みやすい絵本・漫画・雑誌・小説などどんなジャンルでも活字に触れましょう。
本を読む習慣がないお子さんにとって、長文を読むこと自体が抵抗感が生まれ、テストの際にも問題文の中の必要な文章を読み飛ばしてしまうことがあります。
例えば、テストの際に
・間違っているものを選びましょう。→正しいものを答えてしまった。
・合っているものをすべて選びましょう。→合っているものが複数あるのに1つだけ答えてしまった。
という経験はありませんか?問題文の中の答え方のポイントになる文章を読み飛ばしてしまうと、間違った回答に繋がります。
問題文をしっかりと内容を把握し、全て読んで理解して答えるためには、長文に慣れる必要があります。日ごろから活字を読むことで、文章に慣れて大切な言葉を読み飛ばさずに答えることにも繋がります。無理に小説など難しい文章ではなく、漫画やイラストが多めの文字の大きい本などを選んで、本に対する抵抗感をなくしていきましょう。
4つの要素を意識しながら本を読み慣れることで自然とスピードがアップしていきます。
解釈力:音読をする
以前、読解力には音読が大切というお話をしました。
過去の記事はコチラ→読解力を鍛える音読の力を徹底解明!近道は音読だった!
音読をすることで読み飛ばしを防止ししたり、意味を分からずに読んでいた部分の理解を深めたりする効果があります。
また、子どもが音読をしているのを横で大人が聞くことで、発音の間違いなどに気づき正しく直すことができます。正しく文字を追えることは読解力を上げる基本です。
要約力:読んだ本・今日あった出来事についてアウトプットする
今日の出来事や読んだ本などについて、親子で話し合ってみましょう。
「どう思ったの?」
「どうなったの?」
「〇〇ちゃんならどうする?」
などの質問で対話をすることで、自然と読みながら自分の考えや筆者の意図を考えるクセがついていきます。身近な存在の親との会話が読解力を上げる近道です。
出来事や本の内容を要約しアウトプットすることで、「内容を理解し、解釈する力」を自然と身につけられます。
語彙力:わからない言葉をすぐに調べるクセをつける
いくら本をたくさん読んでいても、言葉の意味が分からないままでは文章の意味を掴めません。わからない単語や言葉が出た時に、すぐに辞書などで調べるクセをつけましょう。最初は親がお手本を見せたり、すぐに調べる姿勢を子どもに見せることも効果的です。
手が届く場所に辞書を置いておくことが大切です。語彙力を増やすことで初めて見た文章を読み解くのに役立ちます。
便利な電子辞書はコチラをチェック→中学生向けおすすめ電子辞書4選!選び方や使いやすい電子辞書を徹底比較!
スマホで調べる人も多いですが、情報が間違っていたりメールやSNSなどの誘惑も多く集中が途切れてしまうので辞書や電子辞書を使うことをおすすめします。
三省堂 例解小学国語辞典
小学1年生から使える国語辞典。オールカラーで読みやすいため、小学校低学年のお子さんも気軽に調べられておすすめです。新たに4,000語の大幅増補を実現し、総収録項目数は46,500項目。紙の辞書を購入すると特典でアプリのオンライン辞書が使えます。
小学館 例解学習国語辞典
オールカラーでわかりやすく、豊富なカラー写真やイラストで楽しく読めます!ことばの数も大きく増えて、類書中最大級の約40900語(総収録語数48800)。1100点以上の写真やイラスト、230点以上の表やグラフで理解が深まります。
三省堂 例解新国語辞典
教科書密着型辞書として、最新の教科書からの語句や新語などを含め、圧倒的な情報量で中学受験から高校受験まで長く使える国語辞典です。大型辞典にも載っていない語句・語義まで6万語収録。群を抜く用例と類義語・対義語、[表現][参考][由来][敬語]ラベル、囲み記事で語彙力・表現力・読解力が飛躍します。
語彙力:子どもに対して大人同士の難しい単語も使って話す
子どもに対して話す時に、子供向けの簡単な言葉ばかりを使うのではなく、その場面に適した大人が使用する難しい単語も積極的に使ってみましょう。
わからない単語や知らない語句は調べたり伝えたりすることで、日常の会話の中から語彙力が増えていきます。大人との会話で正しい使用方法などを学び、語彙力がアップします。
要約力:あらすじを語ってみる
文章を読んでみて、本当に読み飛ばさずに内容を理解できているのかを把握するには、あらすじを語ってもらうのが良いでしょう。
「どんなお話だった?」
「それでどうなったの?」
など質問をしながら、内容を話してみましょう。わかりやすく相手にお話をまとめて伝えるあらすじは、大人でもなかなか難しく、文章を要約する力が必要になります。本1冊でなくても、短いコラムや記事などを読んで、まとめてわかりやすく説明するということを日常的にやってみましょう。
解釈力:長文読解の際に印(しるし)をつけながら読むクセをつける
読解力がないと感じているお子さんは、国語のテストを受ける際に文章に何にもしるしをつけていないケースが多く、さらっと読んで問題を解いているお子さんが多いです。
気になる部分や接続詞、登場人物などにしるしをつけながら読むことで、読み終わって問題に取り掛かる際に「あれってどこに書いてあったっけ?」と探す手間が省けます。
国語のテストを受ける際には、文章にどんどん線を引きましょう!
だからと言って手当たり次第に線を引っ張るのではなく、ある程度のポイントを絞って線を引いていきます。
・キーワード、テーマになる言葉
・接続詞「だから・けれども・しかし」など
・登場人物
・気持ち(うれしい・悲しい・怒りなど)
・情景描写
・場面の変化するところ など
線を引きながら読むことでその部分をしっかりと印象付け、さらに問題を解く際に言葉を文章中から見つけやすいというメリットがあります。
自分の中で「登場人物は〇で囲む」「キーワードは□」などルールを決めて慣れておくとさらに問題を解くスピードが上がっていきます。
要約力:面白い文章の読解問題を解いて文章題に慣れる
文章読解が苦手なお子さんの多くは、問題文に興味が持てずにしっかりと読み深められない場合が多いため、できるだけ興味を持てるような面白い文章の読解問題で文章をしっかりと読むクセをつけたいですね。
おすすめは、「謎解きストーリードリル」です。
謎解きの要素のある文章で、興味を持ちながら文章を読み、いくつかの設問に答えていきます。問題自体は難易度はあまり高くないため、まず文章を読んだり、読みながら線を引いたりするトレーニングに使ってみましょう。
国語だけでなく、理科や社会など他の教科の知識を身につけながら文章読解力を上げていけるので興味のある分野から始めるのがおすすめです。
読解力と語彙力を鍛える!なぞ解きストーリードリル 小学国語
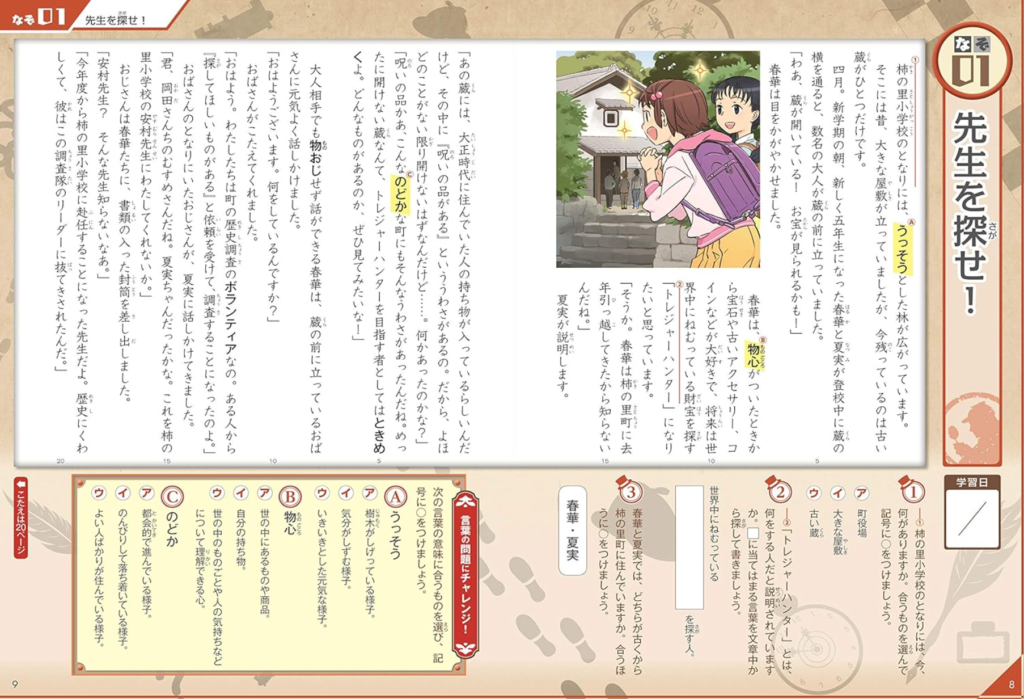
小学生に本当に必要な語彙を厳選し、挿絵入りのショートストーリーを通して楽しく学べる1冊です。なぞ解き仕立てのショートストーリーで読解問題と語彙問題を解いた後は、別冊語彙ドリルで、しっかり復習しましょう。お話の内容を問う読解問題も掲載し、語彙力と読解力を同時に鍛えることができます。別冊語彙ドリルでは本文に登場する語彙をはじめ、覚えておきたい語彙を学べるようになっています。
読解力と語彙力を鍛える!なぞ解きストーリードリル 小学理科
今作では、理科をテーマにしたお話を掲載し、これまでと同様の読解力と語彙力に加えて、理科の知識も身につけることができるような1冊になっています。小学校で習うてこや水溶液、星座などの理科の知識を、なぞ解きを絡めたストーリーで楽しく学ぶことができるようになっています。言葉についての解説はもちろん、お話に登場した理科の知識を章末で詳しく解説しているので、しっかり知識を定着することができます。
読解力と語彙力を鍛える!なぞ解きストーリードリル 小学社会
都道府県にまつわるお話自体の内容を問う読解問題や、歴史に関連する問題など社会を勉強しながら、語彙力と読解力を同時に身に付けることができるような1冊になっています。
読解力アップにおすすめの本
小学生のための ドラえもん 読解力をつけることば図鑑
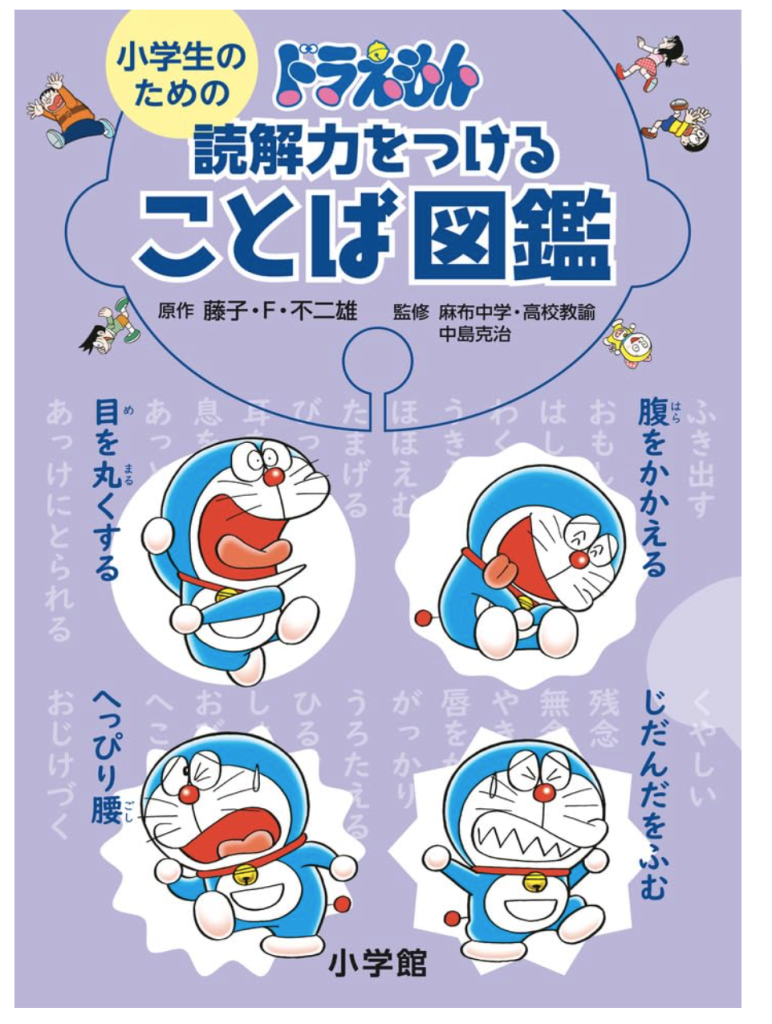
ドラえもんと一緒に読解力を楽しく伸ばす!ドラえもんのマンガとひみつ道具で、楽しく学べる!ドラえもんやのび太くんは、このときどんな気持ちなのかな?この気持ちをことばにすると何だろう?ドラえもんのマンガで主人公の気持ちを読み解く練習から、実際に入試で出される読解表現を、麻布中学校の中島克治先生が解説。
サバイバル + 文章読解 推理ドリル

人気の「科学漫画サバイバル」シリーズの文章読解ドリル版。ハラハラドキドキする12のストーリーの謎を、恐竜や深海魚などの生き物に関する知識でズバリ解き明かす。要点をつかむ「全体読み」→「細かい読み」の2段階読みで、最強の読解力が身につく!
「伝える力」が伸びる! 12歳までに知っておきたい語彙力図鑑
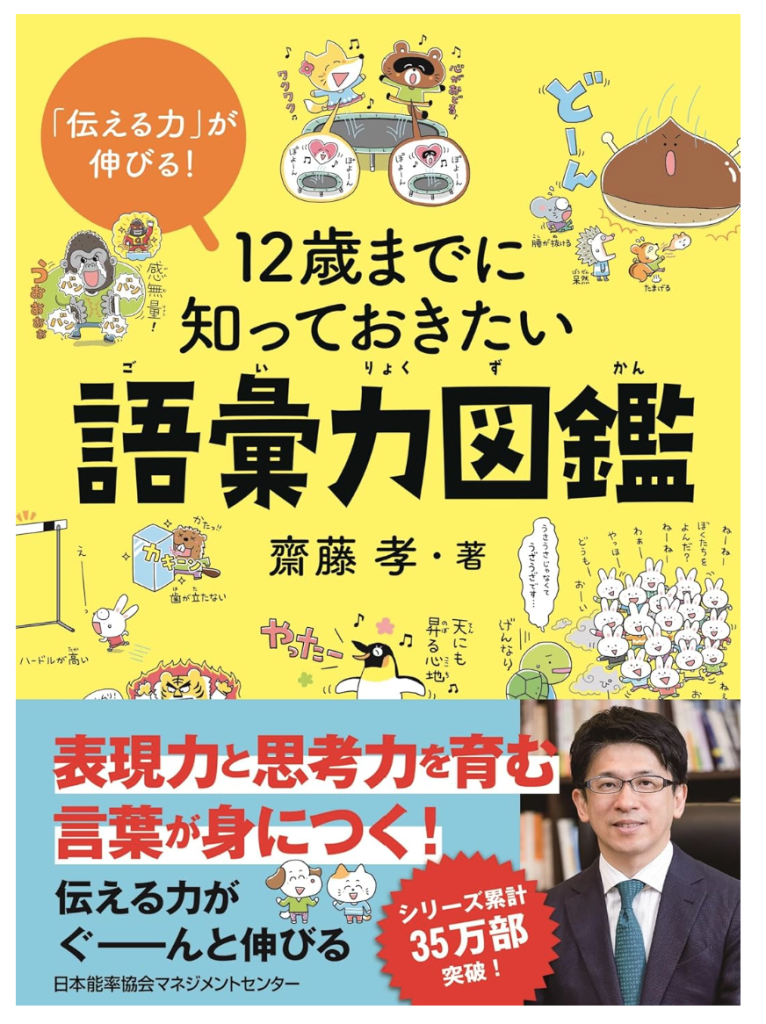
「伝える力」が伸びる! 12歳までに知っておきたい語彙力図鑑
「感情を表現する言葉」に焦点を絞って語彙をあつめて分類。齋藤先生のわかりやすい解説とイラストで、「こういうときはこんな表現が使えるんだ! 」と楽しく自然と語彙力が身につく1冊です。
読解力トレーニング まとめ
読解力は様々な場面で必要になるスキルです。
読解力を上げるには語彙力や文法力が重要ですので、まずは語彙力をアップさせるために親子の会話など、日常の中で言葉を増やしていきましょう。
まずは焦らずにじっくりと文章を読めるように、親子で楽しみながら試してみてくださいね!
【関連記事はコチラ】


